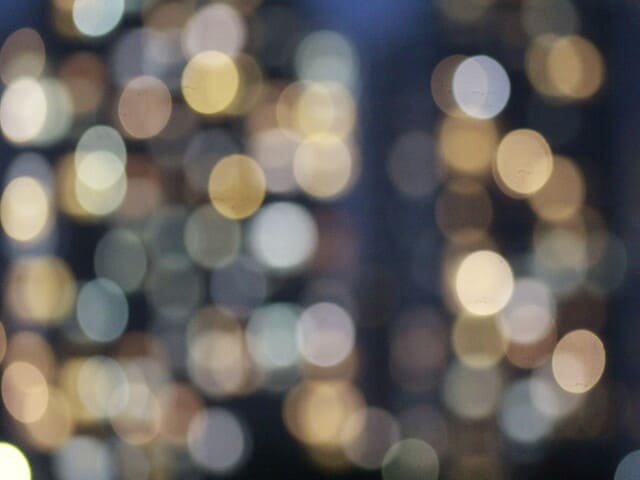もともと照明にそこまでこだわりはなかった。
引っ越しのたびに備え付けの蛍光灯を使い続けてきて、
部屋の明るさに不満を持ったこともなかった。
明るければ十分。そう思っていた。
でも、ある日ふと違和感を覚えた。
仕事終わりにリビングで軽く飲もうとしたとき、
天井のライトがまぶしく感じた。
グラスの中のお酒が、やけに平面的に見えた。
明るさに疲れていたのかもしれない。
それでなんとなく、フロアスタンドをひとつ買ってみた。
初めて間接照明というものを部屋に置いた夜、
部屋の空気が静かに変わった。
その日から、照明というものへの見方が変わった。
部屋の明るさより、空気のトーンを整えたい
間接照明のいいところは、
部屋全体を照らすのではなく、空間にグラデーションをつくってくれることだと思う。
壁に向けて光をあてると、角の影がやわらかくぼやける。
ローテーブルのそばに置いた小さなランプが、会話のトーンを自然と落ち着かせてくれる。
明るい場所と暗い場所が混ざると、視線も自然に散らばる。
結果的に、空気そのものがやわらかくなる。
特にホームパーティーのときは、照明の役割が大きい。
料理や会話に集中してほしいから、部屋は少しだけ暗めにして、
食卓まわりやソファ近くにだけ、光の重心をつくっておく。
そのほうが、なんでもない会話でも印象に残ったりする。
照明は主張しないけど、空気の質を決める静かな演出装置だと思っている。
最近は、照明の数を増やすより、光の高さや向きのバランスを意識するようになった。
光の重心を低くすると、自然と会話も落ち着く。
ひとつの明かりに頼らないことで、空間に余白が生まれる気がする。
暮らしのスイッチは、照明から入れることがある
照明って、ただの設備じゃない。
部屋のどこにどんな光があるかで、生活のリズムそのものが変わる。
疲れた日は、帰宅してまず玄関の照明をつける。
そこからキッチンのペンダントライトをつけて、
リビングのスタンドライトだけを点ける。
そのルーティンが、自分を切り替える合図になっている。
特別な照明を使っているわけじゃない。
IKEAや無印のものも多いし、高級な照明器具を集めているわけでもない。
でも、どこを照らすか、どこをあえて暗く残すか。
そのバランスを整えるだけで、部屋の呼吸が変わる。
明るさではなく、落ち着ける空気をつくる。
それが、僕が照明に求めているもの。
気づけば、スマートスピーカーで音楽を流す前に、
まず照明のスイッチを入れるのが習慣になっていた。
光があると、その場にちゃんと戻れる気がする。
そんな感覚があるから、間接照明って好きなんだよね。